検索サイトからお越しの方で、左にメニューバーが表示がされていない
場合はこちらのOTAIRECORD TOPをクリックしてください。
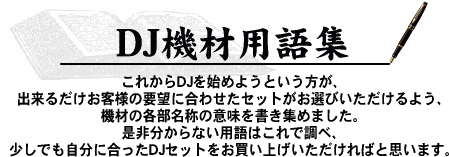
アームとは、ターンテーブルの右側にある先端に針の付いた棒のことを言います。
アームには大きく分けて、S字アームとストレートアームの2通りがあります。
Technicsのように曲がっているのがS字アーム。
VestaxやGEMINIのようにまっすぐなのがストレートアームです。
(VestaxのPDX-2300mk2ProというタイプはJアームといって、Jの形をしたアームになっています。)
S字アームはストレートアームに比べると針飛びがしやすいですが、音質は良いです。
ストレートアームは針飛びしにくいですが、音質ではS字アームの方が勝ります。
針飛びがしやすいといっても、バトルDJが集うTechnics主催のDMC WORLD DJ CHAMPIONSHIPでも、
使うターンテーブルはS字アームのTechnicsですし、
そこでも針飛びなんてせずに皆さん超ド級なヘビーなスクラッチをしています。
なので、S字アーム=針飛びするという考え方は違います。
針の飛びやすさは、アームの違いよりカートリッジの選び方に大きく左右されるので、
針飛びに悩まされるようでしたらカートリッジ交換を考えてみましょう。
ピッチコントロールとは、ターンテーブルの回転を速くしたり、遅くしたりして音程や曲のテンポをコントロールすることを言います。
その調節幅(どこまで速く、または遅く出来るかの幅)はターンテーブルごとに違い、
Technics SL-1200MK5の場合±8、Vestax PDX2000mk2の場合なんと±60%まで変える事が出来ます。
トルクとはSTARTボタンを押し、ターンテーブルが回転する時の力のことをいいます。
DJはプレイ中に頭出しをしたり、スクラッチをしたりと、レコードを常に触っています。
レコードを触っている=プラッター(ターンテーブルの回るお皿のことです)を押さえていることになるので、ずっと触っていると徐々に回転が弱くなっていきます。
トルクが弱ければ弱いほど、すぐに通常の回転に到達するまでの時間がかかってしまいます。
せっかくテンポを合わせたのに、出だしがノロ〜ッと出始めることで全然MIXがうまくいかなかったり、スクラッチをしていてもどんどん回転力が弱まっていって思うようにならなかったりして、それがストレスに感じたりもします。
スクラッチはどうしても力が入ってしまうので、回転も弱くなりやすいです。
MIXであれば、優しく触ることの方が多いので、トルクの弱いターンテーブルでも特別問題にはなりません。
※トルクの表示について!※
これ重要です。
例えばTechnicsのSL1200MK5のトルクは1.5kg/cmです。
そしてもう一つ低価格帯のターンテーブルTT-03は2.2kg/cmとあります。
じゃあTT-03の方が圧倒的に強いじゃないかということになりますが、
トルクの測り方が各メーカーごとに違うんです。
同じ測り方では測っていないので、
実際比べてみたらSL1200MK5とTT-03は同じぐらいの強さだったということもよくある話です。
こちら側としてはメーカー発表の仕様を変えて書くことは出来ませんので、その点はご了承ください。
ミキサーの真ん中下に付いている横に動かせるフェーダーのことです。
これは左右のチャンネルの音量を、ひとつのフェーダーで制御できるものです。
フェーダーを一番左にしてあれば左のチャンネルの音だけ、だんだん右に動かしていくことで右のチャンネルの音が混ざってきて、一番右にフェーダーがいくと右チャンネルの音だけが流れます。
これはクロスフェーダーを動かすことで音がどう動き移るかという設定を調節することです。

このグラフで、縦軸は音量。横軸はクロスフェーダーつまみの位置。赤い線が左チャンネル。
青い線が右チャンネルになっています。
グラフを見ていただければわかると思いますが、クロスフェーダーつまみが一番左にあるときは
左チャンネルの音が100%の音量、右チャンネルの音は鳴っていません。
つまみをだんだん右にずらしていくことで、左右のチャンネルの音が混ざっているのが分かると
思います。
そして一番右にいくと左チャンネルの音が消えます。
ちなみに上のグラフの状態は、フェーダーのカーブが「ゆるい」と呼ばれているときのものです。
では「きつく」するとどうなるか。下のグラフをご覧ください。

先ほどのグラフと同じく、縦軸は音量。横軸はクロスフェーダーつまみの位置。
赤い線が左チャンネル。青い線が右チャンネルになっています。
カーブがきついと、一番左につまみがあるときはもちろん左チャンネルが100%の音量で
鳴りますが少しでも右に動かすと右チャンネルの音が100%で鳴ります。
ちょっとだけ動かせばもう片方のチャンネルの音が出るので、これをパパパッ!と細かくはじきながら
レコードをスクラッチして、音の出す出さないをコントロールしながらアクセントをつけたりします。
ミキサーによっては縦フェーダー(ボリュームフェーダー)のカーブを調節できる物もあります。
これはカーブをゆるくしておくと、音量を上げていった時それに沿って徐々に音量が上がり、
きつくしておくと、ある一線で急激にボリュームが上がるように出来ます。
(バトルDJさんなどはこのカーブも技に組み込んで利用します!!)
本当にちょっと動かしただけでもう片方のチャンネルの音が出るミキサーを『キレのいいミキサー』と言ったりします。
キレがいいほどスクラッチはやり易く、いろいろな技に挑戦できます。
なので、スクラッチDJをはじめ、HIPHOP DJをしたい人はクロスフェーダーカーブ調整の付いたミキサーを選びましょう!!
この調節が出来ないミキサー(スクラッチDJ向けではないミキサー)もありますので、ご注意ください。
これはクロスフェーダーの動きを全く逆にしてくれる機能です。
最初は全く意味が分かりませんが、スクラッチを頑張るDJは、いつかきっと欲しくなる機能なので、
出来るだけ初めからリバースの付いたミキサーを買いましょう。
単純に、フェーダーを右にしたら左の音が流れて、左にしたら右の音が流れます。
スクラッチの練習を続けていると、利き腕が出来てしまいます。
右手でクロスフェーダーを触り、左手で左のターンテーブルを触る練習ばかりしていると、
その逆の動きの、左手でクロスフェーダーを触り、右手で右のターンテーブルを触るということが出来なくなります。
みなさん利き腕じゃない方でご飯は食べにくいはず。そういう現象が起きます。
ここでリバースが付いていると、右手でクロスフェーダーを触り、左手で右のターンテーブルを触ることができるようになります。
右手(クロスフェーダーの手)は全くいつも通り触っていただいて結構です。
クロスフェーダーが逆になっているので、左手で右のターンテーブルを触るといつも通りの利き腕でスクラッチが出来ますよね??
これがリバースのメリットです!!
これはボリュームフェーダー(縦フェーダー)のカーブを調節できるかどうかです。
ボリュームを上げていったときに、メモリ通りにちょっとずつ音量が上がっていくのか、
または最初の方はほとんどボリュームが上がらずに、メモリ7〜9辺りで急に音量が上がるのか?というように、
フェーダーを動かしたときの音量の上がり具合を設定できます。
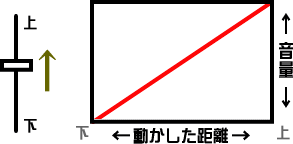
↑このように通常のカーブをAとします。
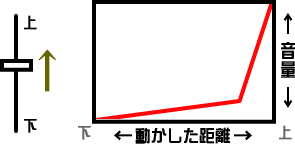
↑このように急に音量の上がる部分があるものをBとします。
ボリュームフェーダーなんだから徐々に上がって入ってくれればいいのに、なぜ??ということですが、
DJはボリュームフェーダーを使った技もたくさんあります。
技によっては、ある部分で急激に音量が上がるように設定しておかないと出来ないような技もあります。
そしてこれはクロスフェーダーカーブ調整ほど、いろんなミキサーには付いていません。
付いているものもあるという方が近いです。(最近発売になったものは付いているものが多いです)
ほとんどのミキサーがボリュームフェーダーカーブ調整が付いていないのですが、
ボリュームフェーダーはクロスフェーダーと違い、ミキサーによってかなりクセがあります。
例えばDMC CHAMPIONSHIPS(Technics主催のバトルDJ世界大会です)の公認ミキサーの、
『SH-EX1200』は、ボリュームフェーダーカーブ調整が付いていません。
メモリ7〜9あたりで急激に音量が上がるように作られています。(Bのようなタイプ)
完全にバトルDJ向きのミキサーなので、こういった作りになっています。
一方Vestaxの『VMC-185XL』や、『PCV-275』は滑らかなカーブになっているので、
徐々にボリュームを上げて曲と曲を混ぜていく、四つ打ち系のDJや、R&BのDJに人気です。(Aのようなタイプ)
クロスフェーダーだけでなく、ボリュームフェーダーでもいろいろな違いがあるんですね。
エフェクトセンドリターンという言葉はさまざまな場面で使われますが、
DJミキサーでの場合、エフェクターを外付けする際の、エフェクター専用の端子のことをいいます。
ミキサーのリアパネルに『SEND(=送る)』と、『RETURN(=戻す)』という端子が付いています。
SENDからエフェクターのINPUTへ。エフェクターのOUTPUTからミキサーのRETURNへつなぎます。
そうすると、ミキサーの中にエフェクターを取り入れたような配線になりますね。
これで、このエフェクターは内蔵ミキサーのようになります。
センドリターン付のミキサーによっては、
各チャンネルのみにエフェクトをかけれるミキサーもあれば、
単純にミキサーから出る全ての音に、エフェクトをかけるミキサーもあります。
これはミキサーによって違います。
じゃあエフェクトセンドリターン端子が無いとエフェクターは外付けできないの?となりますね。
そんなことありません。
どんなミキサーにもエフェクターは付けれます。
ミキサーのMASTER OUT(本来コンポやスピーカーにつなぐ所)からエフェクターのINPUTへ。
エフェクターのOUTPUTから、コンポやスピーカーへとつなげばOKです。
ミキサーから出た音がコンポ、スピーカーまでの間に普通では1本のケーブルでいいものの、
エフェクターをかませることによって音が出るまでの間に接点が増えますよね。
これが音質への影響になるので、エフェクトセンドリターンがついている方が配線も音もキレイに出ます。
音質に影響があるとは言っても、家でやる分には大したことはありませんし、
音に『ザザザッ』とか雑音が入るわけではありません。
全く気にされなくても大丈夫です。
エフェクターをガンガン使いたい人は、そこよりも、
『各チャンネルだけにエフェクトをかけれるミキサーかどうか。』
ここに注目してミキサーを選ぶといいですよ!
★そもそもエフェクターって何?という方はコチラへ。
高域・中域・低域(HIGH,MID,LOW)など特定の周波数を調節し、好みの音を作るための機能です。
最近のDJミキサーはほとんどのものにEQが付いています。
DJミキサーでは大体、高域・低域(HIGH,LOW)の2BANDしかついていないものと、
高域・中域・低域(HIGH,MID,LOW)の3BANDついているものの大きく二つに分かれます。
TECHNO,HOUSE,TRANCEなどの四つ打ち系は、
複雑な周波数を使い分けることで独特の空間を演出する部分があります。
ですので、四つ打ち系のDJは細かく音作りが出来るよう、
EQが3BAND付いた幅広い音域調節の出来るものをオススメします。
+○dBというのは、その音域を○dB強めることが出来るということです。
-○dBというのは、逆にその音域を○dB弱めることが出来るということです。
なので○の値は大きければ大きいほど強めたり弱めたり出来るという事です。
アイソレーターとは、DJの場合イコライザーの強力版のような感じと覚えてもらえばいいと思います。
イコライザーは-○dBと説明しましたが、アイソレーターは-∞(無限)dBという調節が出来ることをいいます。
アイソレーターにも精度があるので必ずしも全て同じとはいえませんが、EQと比べると確かな違いを得ることが出来ると思います。
特に低音をバシッ!!と切ってしまう四つ打ち系のDJには、
アイソレーターのついたミキサーやエフェクターなどを買われる事をオススメします。
アイソレーターの付いたミキサーと、ついていないミキサーの違いはスゴいです。。。
是非ハウス・テクノ・トランスDJはアイソレーター付のミキサーをオススメします!!
これは先程上で紹介したEQを、ボタン一つでそのミキサーの最大限まで切ることの出来るスイッチをいいます。
これが付いていると、『ここで一瞬にして低音を切りたい!』というときに、つまみを思い切り回すのではなく、キルスイッチを押すだけでつまみみを最大まで回した効果が得られるスイッチです。
名前がキル(=KILL:殺すという意味)というだけあって、−の方に切るものしかありません。(一瞬にして+の最大限まで上げるスイッチではないということです)
マイク入力はその名の通りマイクの入力端子があるかないかということです。
マイク入力があれば、ミキサーに直接マイクを接続し、しゃべってスピーカーから音を出すことが出来ます。
マイクの音を調節できるEQのことを言います。
これにも2BAND、3BANDと、ミキサーによって違いがあります。
マイクは大体また別のミキサーにつないで使うことが多いので、
こだわった使い方をしなければそこまで要求されない機能です。
まずBPMとは何か?これは『BEAT PER MINUTES(ビート パー ミニッツ)』の略で、1分間に何拍あるか?ということです。
1分間その曲に合わせて拍を取るように手を叩けば、その曲のBPMがわかります。
例えば1分間叩き続けて115回だったとします。そうすると、その曲のBPMは115となるわけです。
曲のテンポが速ければ手を叩く回数も増えるので、単純にテンポの速い曲はBPMが大きい数になります。
BPMカウンターとはBPMをカウントしてくれる機能です。ミキサーやエフェクターに付いているものもあります。
ミキサーに付いていた場合、ターンテーブル(またはCDJ)からミキサーに入力された音をミキサーが聞き取り、およそのBPMをデジタル表示してくれます。
『BPM=曲の速さ』なので、極端にBPMの違うものはMIXしづらく、BPMの近いものはどちらかを少し調節すればいいので、MIXもしやすい(テンポもあわせやすい)です。
BPMカウンターがあると、表示されたBPMを目安にしてピッチ調節が出来るので、初心者さんがDJを始める時は役に立つ機能といえます。
ただミキサーは人間では無いので、変わったテンポの曲や、ミキサーが聞き取りにくい曲はうまくBPM表示がされないことがあります。
TECHNO,HOUSE,TRANCEなどの四つ打ち系の曲は『ズン、ズン、ズン、ズン』とほぼ一定の間隔で低音が入るので、ミキサーも比較的聞き取りやすく、うまく表示しやすくなります。
エフェクターとは、音にエフェクト(効果)を加えるものです。
ギターで説明するとわかりやすいでしょうか。
ギターは普通に弾けば『ぽろろろろ〜ん』と音がなりますが、ロックバンドなどのギタリストは『ジャジャーン!!』とノイズを利用したようなざらついた音を出しますよね。
あれがエフェクターの効果です。
もとある音(ぽろろろ〜ん)に効果を加え、新しい音(ジャジャーン!!)にして、同じ音程でも本来とは全然違う聞かせ方が出来ます。
DJでのエフェクターは試しにいろいろなエフェクトを聞くことが出来るようにしてみましたので、コチラのページもご覧ください。
サンプラーとは、サンプリングする機材のことを言います。
ではサンプラーとは一体何なのか?
それは、ジャンル問わず見られる音楽の表現手法で、既存の曲の一節を抜き出すことを言います。
曲を聴いていると、『あれ?今のフレーズ○○の□□って曲のサビのところじゃん!!』ということがあります。
それは、○○さんの□□という曲のサビのところをサンプリングして使っているからです。
よくHIPHOPに見られる手法ですね。
サンプリングして作られた曲を『この曲、○○の□□ネタだよ』なんていう言い方をしたりします。
(○○の□□という曲をネタにして(サンプリングして)、自分の曲に使っているからです。)
これは著作権に反することになりますね。
『著作権とは、ある人が作った曲はその人に権利がありますよ!
だからもしカバーとかするならちゃんとお金を払って了解を得てからカバーしてくださいね!』
という権利のことをいいます。
単純に説明すると、Aさんの曲を勝手にパクってはダメですよという決まりです。
なので、大物アーティストさんたちはみんな著作権を得て、曲を作り、販売しているわけです。
曲だけで無くても、サンプリングはいろいろなところから出来ます。
ドラム缶を叩く音や、動物の鳴き声、足音、人の笑い声、野菜を切る音などなど。
おもしろい音ネタをどうカッコよく生かすか?というのも重要なポイントになってきます。
…長々と説明しましたが、ミキサーに付いているサンプラーはそんなに大きなものではなく、
約○秒というかなり少ない時間サンプリングしか出来ません。
なので、使い方としては『Yeah!』とか、『ズン!(キックの音)』とか単発系を取り込んで、
曲の中で味付けとして使ってみるといいですよ!!
レゲエDJなら『プゥゥウウウアアアアッ!』っというホーンの音ぐらいなら取りこめるので、
フロアをあおる大きな武器にもなります!
検索サイトからお越しの方で、左にメニューバーが表示がされていない
場合はこちらのOTAIRECORD TOPをクリックしてください。